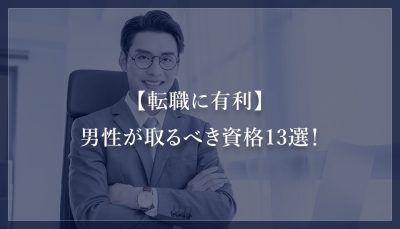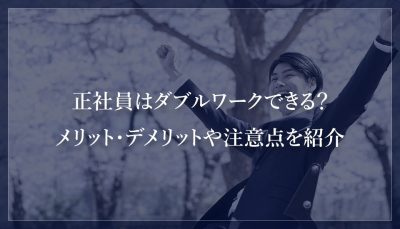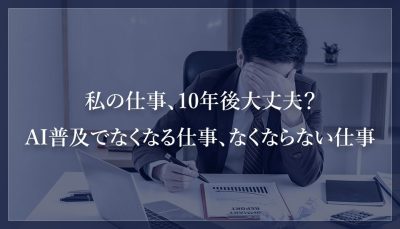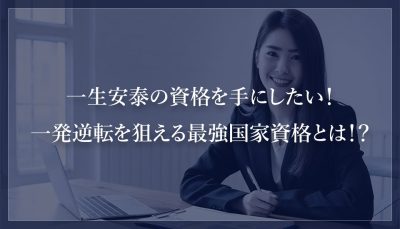フリーランス・個人事業主の就労証明書の書き方!作成のポイントを解説
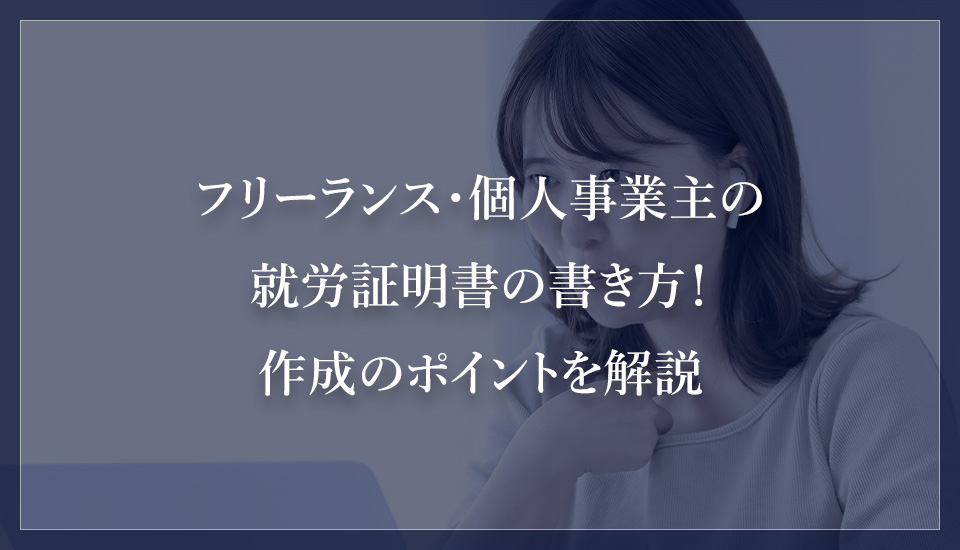
「お子さんを保育園に預けたいけど「就労証明書」の提出を求められた。会社勤めじゃない私たちはどうすればいいの?」
フリーランス・個人事業主の皆さん、「就労証明書」の書き方で困っていませんか?
ここでは、お子さんを保育園に預けるときに必ず必要となる就労証明書について、フリーランス・個人事業主の就労証明書の書き方を解説いたします。
就労証明書の作成のポイントを分かりやすくご説明いたしますので、ぜひ参考になさってください。
目次
就労証明書とは?
就労証明書とは、働いていることを証明するための書類です。
保育園にお子さんを預けたいときに必要な書類のひとつでもあります。
就労証明書には、就労時時間や雇用形態、収入などを記載する欄があります。
これらの情報をもとに、自治体は保育が必要か否かを判断するのです。
お子さんを保育園に入園できるかどうかを左右する大切な書類、それが就労証明書です。
そのため、希望する保育園にお子さんを入園させるためには、この就労証明書を事実に基づいてきちんと作成しなければなりません。
会社員の方であれば、このような書類は、会社に言えば、発行してくれるのですが、フリーランスや個人事業主の皆さんは、雇用主がいないので、ご自身で作成しなければならないのです。
フリーランス・個人事業主の就労証明書の書き方
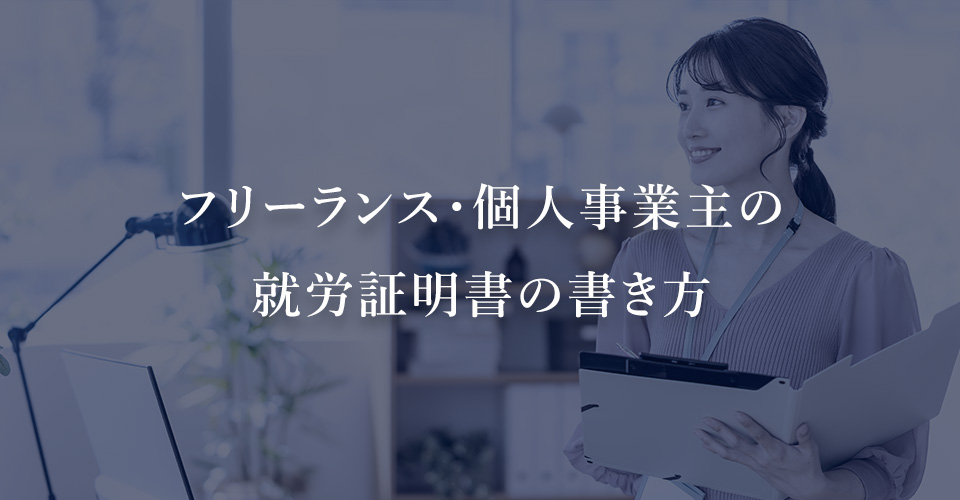
それでは早速、フリーランス・個人事業主の就労証明書の書き方についてレクチャーしてまいります。
それぞれの項目について、記入する際のポイントも解説いたします。
証明日
この欄には、就労証明書を作成した年月日を記入します。
自治体によっては、「証明日から2ヶ月以内の証明書に限る」といった規定があるところもあります。
証明日は、自治体へ提出する日に合わせて記入するようにしましょう。
事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名・記載者連絡先など基本情報
事業所名には、屋号があれば屋号を書きます。
屋号がない場合には、ご自身の氏名を記入します。
代表者名・担当者名もご自身のお名前です。
所在地は、フリーランス・個人事業主として活動している事務所の住所を記載します。
開業届を提出している方は、事業所として登録した場所の住所を記入しましょう。
自宅でお仕事をされている場合は、自宅の住所を書いてください。
電話番号欄には、仕事場の番電話番号ではなく、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
①業種
業種を書く欄には、挙げられている業種のなかから、ご自身の職種に該当するものを選びチェックを入れます。
フリーランス・個人事業主の方で、在宅ワークをされている方は、該当する業種がないかもしれません。
その場合は、「その他」にチェックを入れて、かっこのなかに、「Webライター」「動画クリエイター」など、ご自身の職種を記入するようにしてください。
②本人氏名・生年月日
この欄には、ご自身のお名前と生年月日を記入します。
生年月日は、西暦で記入するようにしましょう。
ほかの項目も西暦で記入するようにします。
③雇用(予定)期間等
この項目には、「無期」「有期」を選ぶ欄があります。
フリーランス・個人事業主をこの先続ける予定であれば、「無期」にチェックをしましょう。
「期間の開始年月日」を記入する欄には、あなたが事業を始めた日付もしくは、開業届を提出した日付を記入しましょう。
④本人就労先事業所
ここには、書類の欄外の「事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名・記載者連絡先など基本情報」で記入した「事業所名」の住所と、実際の就労場所が異なる場合に記入します。
例えば、企業に常駐するというスタイルでお仕事をされている場合は、自宅や事業所とは別に、勤務している企業の名前と住所をここに記載します。
⑤雇用の形態
この欄は、いくつか挙げられている形態からご自身に当てはまるものを選んでチェックするようになっています。
フリーランス・個人事業主の場合は、「自営業主」という欄がありますので、ここにチェックを入れてください。
ただし、ご家族が経営する事業に従事している方に関しては、「自営業専従者」または「内職」いずれかになると思いますが、これについては自治体ごとに解釈が異なります。
各自治体で確認して記入するようにしてください。
⑥就労時間
就労時間が決まっている場合は、「固定労働の場合」という欄に記入します。
不規則な働き方である場合は、「変則就労の場合」の欄に、1ヶ月または1週間あたりの合計就労時間を記入するようにしてください。
ちなみに、フリーランス・個人事業主の場合、正社員と同様に1日あたり8時間以上の就労時間があれば、入園審査に有利です。
ただし、本当にそれだけの時間就労しているのか証明するための書類(業務委託契約書、請求書、作業日報など)の提出を追加で求められることもあります。
⑦就労実績
提出日からさかのぼって、直近3ヶ月間の実績を記入します。
フリーランス・個人事業主として開業したばかりという方は、見込みで大丈夫です。
また育休で直近3ヶ月の実績がない場合は、育休を取得する前の就労実績で構いません。
この場合、産休・育休などを取得した月は除くようにしてください。
⑧〜⑩育児休業の取得に関連した欄
フリーランス・個人事業主の場合、産前・産後休業制度は適用となりません。
書類の⑧〜⑩の欄は、未記入でも構いません。
⑪復帰(予定)年月日
産後すぐに事業を再開している方は、実際の年月日を、また現在妊娠中で、産後すぐに仕事に復帰する予定の方は、復帰予定の年月日を記入します。
⑫育児のための短時間勤務制度利用有無
産後、育児のために就労時間の変更を行なっている場合は、変更後の就労時間を具体的に記入してください。
⑬保育士等としての勤務実態の有無
過去に保育士やベビーシッターなど保育に関連する仕事に従事したことがある方、現在その職に就いている方は「有」にチェックしましょう。
⑭備考欄
備考欄には、追記すべき特別な事情がある場合に記入します。
例えば、繁忙期と閑散期では就労時間に変動がある場合、業務委託先が複数ありそれぞれ契約時間が異なる場合、開業したばかりで実績がほぼない場合、宿泊出張の回数などです。
フリーランス・個人事業主の方は、追記事項がある場合、保育の必要性を訴えるためにも、特に詳しく記入することをおすすめします。
まとめ
就労証明書は、各自治体の窓口で直接もらうか、Webサイトからもダウンロードできます。
自治体によって書式が若干異なりますので、必ずお住まいの自治体から手に入れるようにしてください。
また事前に、お住まいの自治体の選考基準に沿った内容で申請できるように、事前に選考基準をリサーチしておきましょう。
保育園の申請には、就労証明書のほか、開業届や確定申告書の控えなども必要になります。
必要な書類は、あらかじめ用意しておきましょう。
また指定された追加の資料も速やかに用意するようにしてください。
どうしても選考基準にご自身の条件が届かない場合でも、一応は提出をしてみましょう。
そのうえで、許可されなかったときのことも考えて、認可外保育・民間学童なども視野に入れておくことをおすすめします。