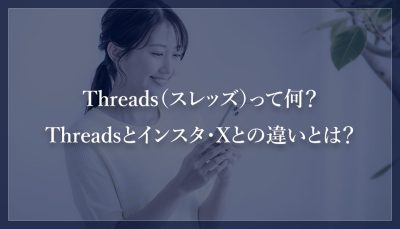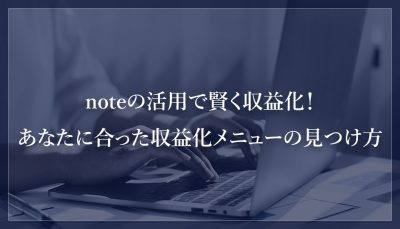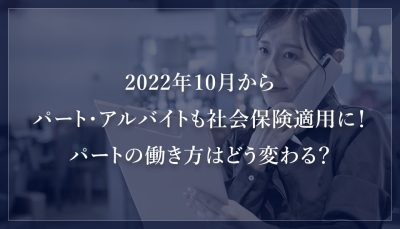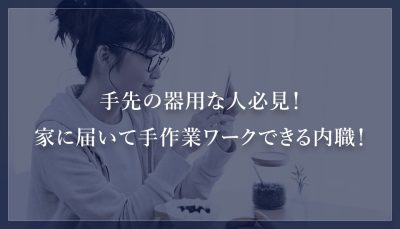副業するなら社会保険に気を付けて!2箇所以上から給与をもらう場合はどうなる?
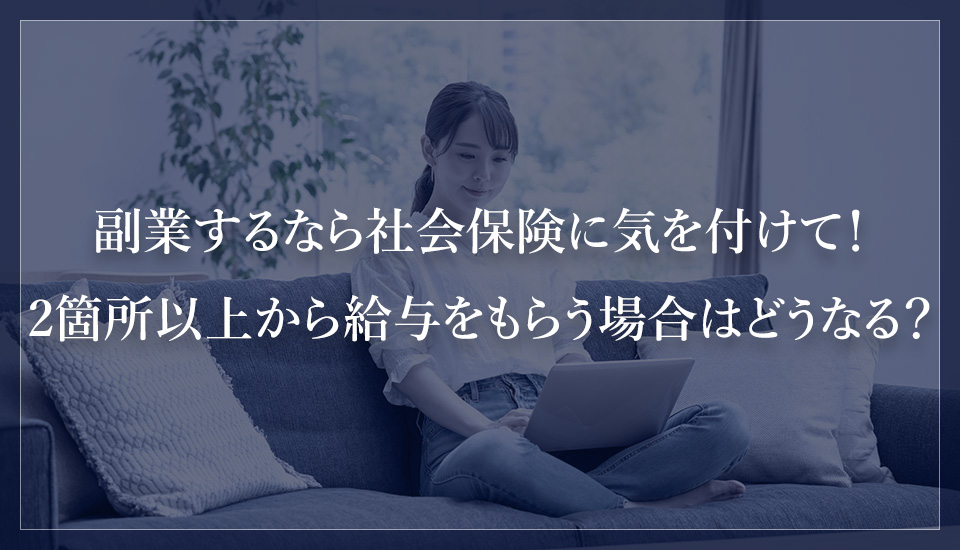
働き方改革や収入の多様化により、副業を始める会社員が増えています。
しかし、副業で収入を得るときに気をつけたいのが社会保険についてです。
会社員にとって社会保険は、毎月の給与から自動的に天引きされるため、意識したことがないという方がほとんどだと思います。
それだけに、副業をすることで思わぬトラブルや負担増につながる可能性もあります。
ここでは
- 会社員、個人事業主が加入している社会保険
- 副業で2箇所以上から給与があるときの注意点
この2つの視点から、副業の際の社会保険についてご紹介していきます。
目次
会社員、個人事業主が加入している社会保険について
社会保険とは、国が定める公的な保険制度の総称です。
おもに健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険・国民年金・国民健康保険を指します。
どの制度に加入するかは「雇用形態」や「働き方」によって決まります。
それでは、会社員と個人事業主の場合に分けてみていきましょう。
会社員(給与所得者)の場合
会社員は通常、勤務先の会社を通じて社会保険に加入します。
健康保険
業務中や通勤中以外での怪我や病気、疾病による休業、出産、死亡に対する保険制度です。
医療費の一部負担、出産手当金、傷病手当金などが給付されます。
給料の額を基に保険料が決まり、原則、従業員と会社で半分ずつ支払います。
厚生年金保険
老後の生活や障害が起きた場合、死亡した場合に備えた保険制度です。
老後の年金のほか、障害年金・遺族年金の基礎となります。
毎月保険料を納めることで、老後に年金を受け取ることができる老齢年金と、障害を負った場合に受け取れる障害年金、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる遺族年金があります。
日本の年金制度は、2階建方式です。
そのため、会社員は、「国民年金保険」と「厚生年金保険」の両方に加入するようになります。
保険料は、健康保険と同じく、給与の額を基に決まり、会社と折半します。
雇用保険
従業員の雇用の安定と促進を目的とした保険です。
失業時の失業給付や、育児休業時の給付金、教育訓練給付金などが受けられます。
労働者災害補償保険(労災保険)
業務災害や通勤災害に対して給付が行われます。
介護保険(40歳以上)
介護サービスを受けるための制度。
原則40歳になった月から健康保険料と一緒に納付します。
こちらも給与の額が基になり、会社と折半して支払います。
65歳以上の人は、65歳になった月から、年金からの天引きで市区町村に納めます。
個人事業主(フリーランス)の場合
一方、副業で事業を営む人や専業フリーランスは、会社を通じて社会保険に入ることができないため、以下の制度に自身で加入します。
国民健康保険
業務中や通勤中以外での怪我や病気、疾病による休業、出産、死亡に対する保険制度です。
自治体が運営し、医療費の一部負担や出産育児一時金などが給付されます。
国民健康保険料は、本人の所得や世帯状況に応じて決まります。
国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は原則加入します。
毎月保険料を納めることで、老後に年金を受け取ることができる老齢年金と、障害を負った場合に受け取れる
障害年金、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる遺族年金があります。
年金制度の2階建方式のうち、個人事業主は、「国民年金保険」のみに加入していることになります。
介護保険(40歳以上)
介護サービスを受けるための制度。
原則40歳になった月から健康保険料と一緒に納付します。
介護保険料は、本人の所得や世帯状況に応じて決められます。
65歳以上の人は、65歳になった月から、年金からの天引きで市区町村に納めます。
国民年金基金・iDeCo(任意)
将来の年金を補強するための制度です。
任意なので、入らなくても構いません。
労災・雇用保険は原則なし
一人親方その他の自営業者、中小事業主には、労働者災害補償保険の特別加入制度があります。
副業で2箇所以上から給与があるときに気をつけたい保険のポイント
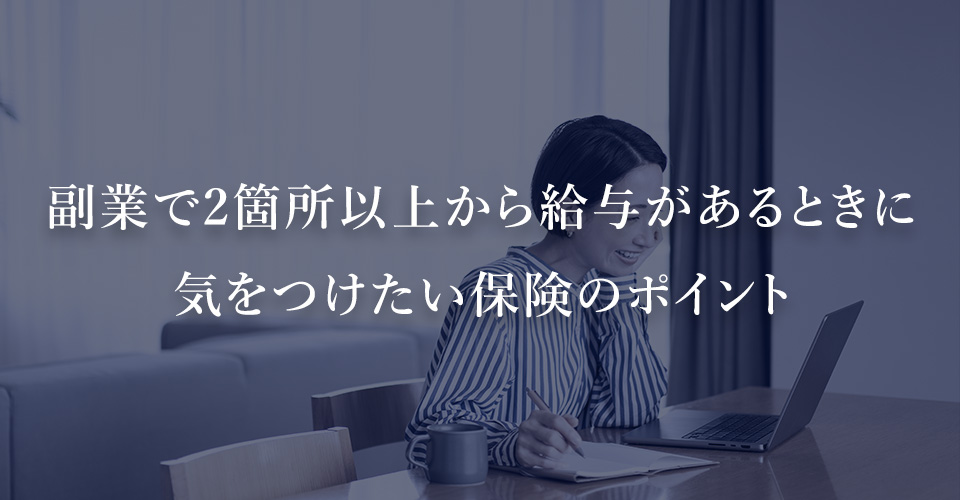
副業のスタイルには大きく分けて「業務委託やフリーランスとして収入を得るケース」と「別の会社から給与をもらうケース」があります。
特に注意が必要なのは 2つ以上の会社から給与をもらう場合です。
2つ以上の勤務先から給与を得ている場合、どの会社で社会保険に加入するかが問題となります。
それぞれの保険のルールは次の通りです。
雇用保険の加入条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- 継続して31日以上の雇用見込みがある
これら両方の加入条件を満たす場合は、加入義務が発生します。
健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件
2022年10月1日から、パート・アルバイトも社会保険の加入義務が生じるようになりました。
加入条件は、以下の2つのうちのいずれかです。
- 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上
- 下記の5つの条件をすべて満たしている(1の加入条件を満たしていない場合も加入義務が発生します)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 2か月を超えて使用されることが見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 上記1の一般被保険者が常時100人超の企業(特定適用事業所)に勤めていること
上記の条件を満たした場合、本業の会社では、前述のすべての保険に加入することになります。
また、パートとして働いている副業の方では、雇用保険を除くすべての保険に加入することになります。
この場合、本業と副業の収入を合算した金額を基に、保険料が算出されます。
複数の会社で健康保険・厚生年金の加入条件を満たす場合の手続き
複数の会社で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たす場合、自身でメインとなる会社を選択し手続きを行なう必要があります。
日本年金機構のHPから、2枚の用紙をダウンロードします。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」と
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」です。
提出先は、メインに選択した会社を管轄する年金事務所や健康保険組合です。
複数の会社で勤務をするようになった日から10日以内に提出しなければなりません。
窓口に持参するか、郵送、もしくは電子申請も可能です。
メインに選択しなかった事業所で加入していた社会保険に関しては、「健康保険・厚生年金保険 資格喪失届」の提出と「健康保険被保険者証」の返却が必要になる場合があります。
まとめ
特に副業によって収入が増えることは喜ばしい一方で、社会保険の制度は複雑に絡み合っています。
社会保険料は毎月の手取りや将来の年金額に直結するため、副業を始める際は必ずシミュレーションしておくことをおすすめします。
また加入義務があるにも関わらず、入らなかった場合、罰則・罰金が適用されます。
健康保険法第208条 では、事業主が正当な理由なく届出を行わない場合や、虚偽の届け出を行った場合などは、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
また、健康保険や厚生年金保険に未加入であることが後から発覚した場合、最大2年間さかのぼって加入義務が発生する可能性があります。
社会保険料の時効は2年なので、2年間分の社会保険料を一括納付しなければならないことになる可能性があります。
副業はしたいけど、健康保険や厚生年金保険に加入したくないという方は、加入条件を満たさないよう勤務時間等の調整が必要です。