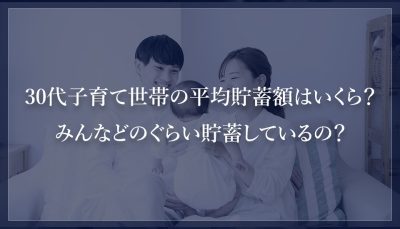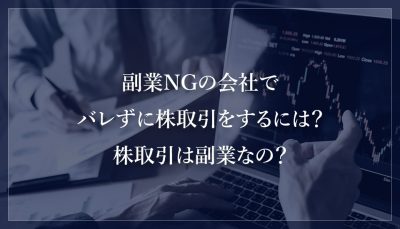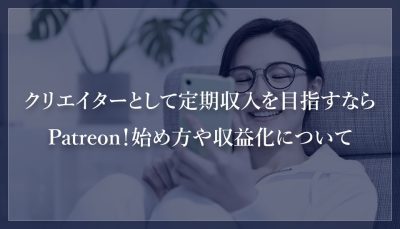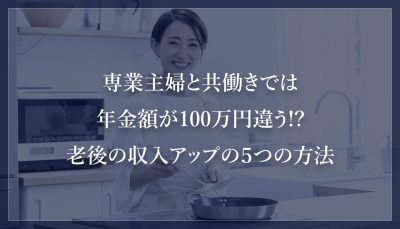女性の貯蓄平均額は800万円超え!?貯まる貯蓄方法とは?
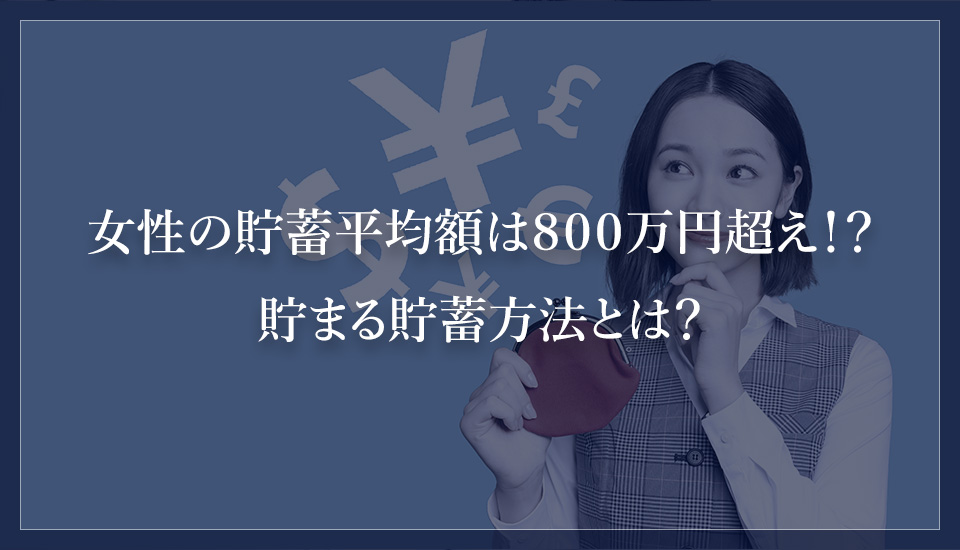
女性の貯蓄は多いのか?
データを基に、女性の貯蓄額についてご紹介するとともに、貯まる貯蓄の方法についてもご紹介いたします。
目次
独身女性の年収別平均貯蓄金額
まずは、独身女性の年収別平均貯蓄額について見ていきましょう。
2019年全国家計構造調査のデータを見てみると
年収100万円未満で、295万円
100~150万円未満は、217万円
150~200万円未満278万円
200~250万円未満325万円
250~300万円未満395万円
300~350万円未満439万円
350~400万円未満376万円
400~450万円未満486万円
450~500万円未満522万円
500~550万円未満814万円
550~600万円未満1,026万円
このようになっています。
年収400万円未満の層については、年収と貯蓄額に関係性はさほど見られませんが、
年収400万円以上の層については、年収が増えるにつれて、平均貯蓄額も高くなっているのが分かります。
男女含む独身者の年収別貯蓄額の中央値
それでは次に、男女問わず単身者の貯蓄額の中央値を年収別に見ていきましょう。
令和5年の家計の金融行動に関する世論調査によると、以下のようになっています。
無収入の方の中央値は、318万円です。
300万円未満は、663万円
300~500万円未満1,019万円
500~750万円未満1,943万円
750~1,000万円未満3,837万円
1,000~1,200万円未満634万円
1,200万円以上17,011万円
ご覧のように、年収が高くなるほど貯金額が増えています。
貯めている人がしている貯蓄の方法とは?
貯蓄の方法はいろいろありますよね。
預貯金、投資商品、保険商品などさまざまです。
ここでは、貯めている人がどのような方法で貯蓄しているのかをご紹介していきます。
「令和5年 家計の金融行動に関する世論調査」によれば、以下のようになっています。
2人以上世帯において、一番多いのは預貯金で563万円となっています。
次に多いのが、株式の253万円、続いて生命保険の153万円、投資信託119万円と続きます。
このほか、個人年金保険、債券、財形貯蓄、損害保険などがあります。
単身世帯についても、一番多いのは預貯金で408万円となっています。
次いで、株式で225万円、投資信託106万円、生命保険72万円、個人年金保険48万円、債券41万円と続きます。
このほか、2人以上世帯同様、損害保険、財経貯蓄、金銭信託がありますが、2人以上の世帯に比べて、あまり活用されていないようです。
いずれの世帯も一番大きな割合を占めているのが預貯金です。
次いで、株式、投資信託といった投資商品が続いています。
そのあと、生命保険、個人年金保険といった保険商品が続いているのが特徴です。
独身女性の年代別平均貯金額
次に、独身女性の年代別平均貯金額について見て見ましょう。
一番貯蓄をしているのは、60代で1,423万円です。
ついで、70代の1,217万円、50代1,111万円となっています。
30歳未満の平均貯蓄額は187万円と、200万円を切っています。
30代で408万円、40代で800万円と増えていき、60代でピークを迎え、70代以降は、平均貯金額は減少傾向になります。
共働き夫婦の平均貯金額
ここまでおもに単身者の平均貯蓄額を見てまいりましたが、ここで2人以上世帯の夫婦共働き世帯について見ていきましょう。
令和3年、家計の金融行動に関する世論調査(令和3年)によると、共働き夫婦の平均貯金額は、平均値が1,067万円、中央値が300万円です。
また子どもがいる夫婦の平均貯金額は、平均値が1,212万円、中央値が400万円となっています。
共働き夫婦にくらえて、中央値は70万円も高くなっています。
子どもの将来のために、蓄える家庭が多いという結果であると言えます。
女性のライフステージに沿って必要な貯蓄額逆算
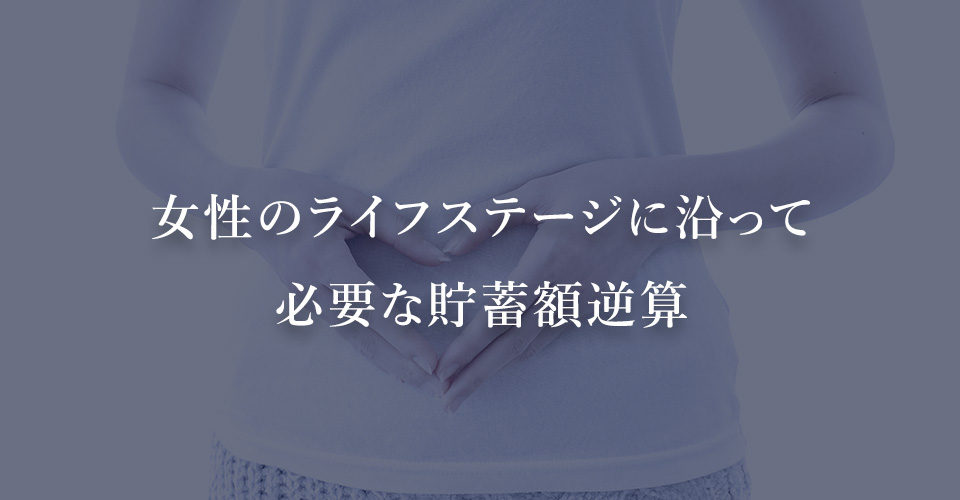
ここまで、おもに女性の皆さまの平均貯蓄額を見てまいりましたが、ここからは女性目線で見た、ライフステージ別必要なお金から逆算する必要貯蓄額について見ていきたいと思います。
ここでは、女性のライフステージを6つに分けて見ていきます。
結婚~妊娠・出産
「ゼクシィ結婚トレンド調査2023」「新婚生活実態調査2023」によると、結婚資金の全国平均は523.2万円でした。
妊娠時にかかる費用は、おもに妊婦検診費用になりますが、約7万円、出産時の入院・分娩費用の全国平均は、約50万6,000円となっています。(公益社団法人 国民健康保険中央会 出産費用の全国平均値、中央値/平成28年度参照)
出産については、出産一時金42万円がもらえるので、差し引くと、16万円前後必要になります。
育児・教育資金
文部科学省の令和3年度の学習調査によると、幼稚園から高校を卒業するまでの15年間で、全て公立校の場合で約574万円、すべて私立の場合は約1,840円の費用がかるとされています。
文部科学省の調査によれば、国立大学で2,425,200円、公立大学で2,519,135円、私立文系大学で4,107,759円、私立理系大学で5,417,532円、私立医歯系大学6年間で23,543,099円必要だということです。
さらに、これらの費用に加え、通学費、教材、受験費用、一人暮らしの費用などがかかってきます。
住宅購入資金
住宅資金は、3,000万円~5,000万円とエリアや住宅のタイプによって変わってきます。
首都圏は、全国平均に比べ、かなり高くなりますので新築だけでなく中古やマンションも選択肢に入れるとよいでしょう。
疾病・介護費用
公益財団法人 生命保険文化センターの調査によれば、直近の入院時の自己負担費用は、平均198,000円となっています。
高額療養費制度を利用した人については利用後の金額から算出していること、直近の入院時の逸失収入も併せて見てみると、平均は30.2万円となっています。
万一の入院の備えとしては、最低50万円前後の貯金や保障が必要だと言えます。
老後の生活
老後1ヶ月あたりの平均的な収入・支出を夫婦世帯、独身世帯別で見て見ましょう。
総務省統計局令和5年の調べによれば、夫婦世帯の月額の支出は282,497円、実収入は244,580円、37,916円足りない計算になります。
単身世帯で言えば、支出が157,673円、実収入が126,905円、不足が30,768円となっています。
単純計算すれば、月々3万円足りないとすれば、90歳までの25年間で900万円が不足するという計算になります。
まとめ
ライフステージに合わせて計画的に貯蓄をしていくことは大変重要です。
ライフステージに関わらず、予定外の出費が必要な場合があります。
緊急予備資金として、毎月の生活費の6ヶ月分を目安に貯めていくことをお勧めいたします。
万が一に備えて、また将来に備えて、コツコツと貯蓄していくことが大切です。
そのための金融商品などもぜひ検討してみてください。