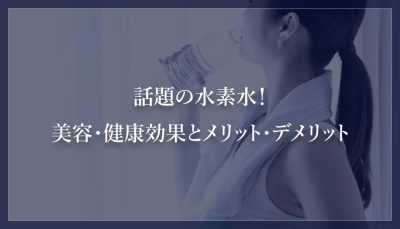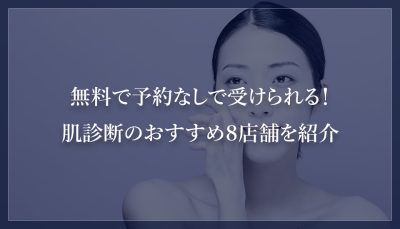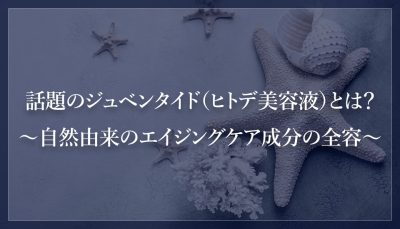体に必要な5大栄養素の3つの役割と多く含まれる食品を解説!
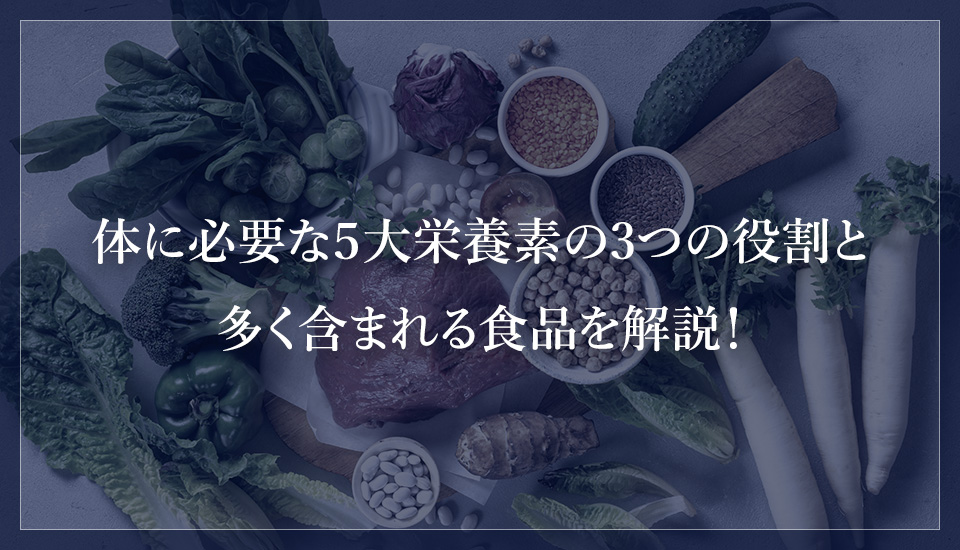
皆さま、5大栄養素ってご存じですか?
5大栄養素とは、炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルの5つの栄養素のことです。
これらの5つの栄養素には、それぞれ役割があります。
そしてそれらの役割は、私たちが健康でいるために必要不可欠なものです。
ここでは、私たちが健康を保つために必要なこの5つの栄養素について、その役割について詳しくご紹介いたします。
5大栄養素の3つの役割
私たちの体に必要な5大栄養素には、次の3つの役割があります。
それでは、それぞれの役割について見ていきましょう。
身体を動かす
身体を動かすためのエネルギー源となる栄養素として、脂質、たんぱく質が挙げられます。
この2つの栄養素は、エネルギー産生栄養素と呼ばれています。
身体をつくる
たんぱく質、ミネラルは、身体を作るための材料になる栄養素です。
身体の調子を整える
身体の調子を整え、健康維持に欠かせない栄養素として、ミネラル、ビタミンが挙げられます。
5つの栄養素の主な働きと、多く含む食品について
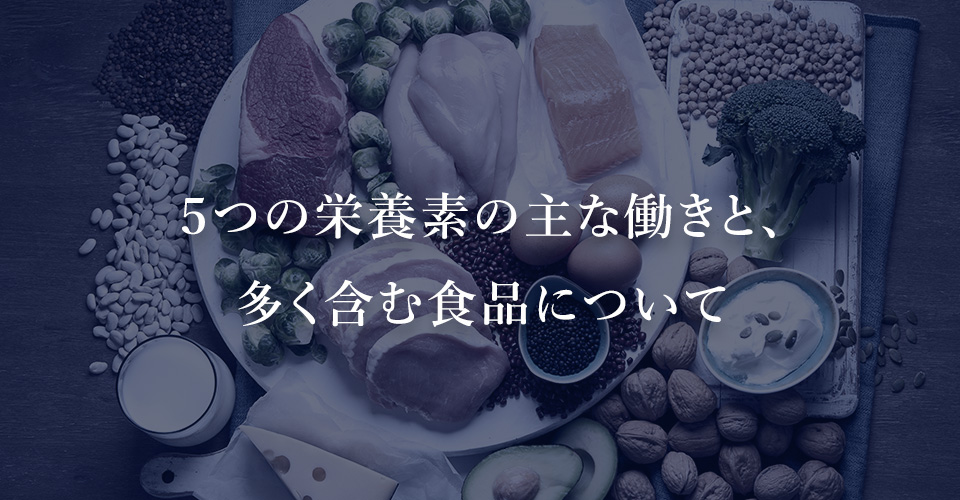
それでは、5つの栄養素それぞれについてのおもな働きと、その栄養素を多く含む食品について見ていきましょう。
炭水化物
エネルギー源になります。
炭水化物のなかには、消化吸収されてすぐに脳や身体のエネルギーとなる糖質と、体内の消化酵素では消化できない食物繊維があります。
糖質について
糖質は、1gあたり約4kcalのエネルギーを産生し、おもに脳や筋肉などといったブドウ糖しかエネルギー源として利用できない組織にブドウ糖を供給します。
糖質は、消化吸収にかかる時間が短いので、すぐにエネルギーになるのが特徴です。
糖質が不足すると、エネルギー不足の状態になり、疲れやすく集中力がなくなります。
また、糖質が不足すると、私たちの身体は不足分を補うために、筋肉を分解してたんぱく質をエネルギー源として利用します。
エネルギーとして使われなかった糖質は、肝臓、筋肉に取り込まれます。
しかしながら、蓄えることができる量は限られているため、残りは中性脂肪として蓄えられます。
これは、飢餓に備えられた身体の仕組みなのですが、残った糖質が多くなり中性脂肪としての蓄えが多くなると、肥満や生活習慣病の原因になります。
糖質を効率よくエネルギーに変えるためにはビタミンB群が必要です。
余分な糖を身体に蓄えないようにするために、ビタミンB群を一緒に摂ることをおすすめします。
食物繊維について
一方、食物繊維は、人の消化酵素で消化できない栄養素です。
水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維に分類されます。
体内に入った食物繊維は、小腸で消化吸収されずに大腸で体調の環境を整える腸内細菌のエサとなり、菌を増やす役割を担っています。
そのため、便秘を予防する整腸効果があるとともに、血糖値上昇の抑制、血中コレステロール濃度の低下などといった多くの働きがあります。
炭水化物は、ご飯、パン、麺類、芋類などに多く含まれており、なかでも、ご飯、パン、麺類、砂糖・ハチミツには、糖質が多く含まれています。
また、食物繊維を多く含む食品としては、穀物、豆類、野菜、果物、きのこが挙げられます。
脂質
エネルギー源であると同時に体温を維持したりホルモンを生成する働きがあります。
1gあたり、約9kcalのエネルギーを産生し、炭水化物やたんぱく質よりも多いエネルギーを生み出すことができるとされています。
そのため私たちの身体は、脂質を優先的にエネルギー源とする仕組みになっています。
脂質は、神経組織や細胞膜、ホルモンなどの形成に欠かすことのできない栄養素です。
また、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKといった脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きを担っています。
脂質は、小腸で消化され、いろいろな代謝経路を経て、効率の良いエネルギー源として利用されます。
ここで余った脂質は、中性脂肪として蓄えられます。
そのため、脂質を多く摂取すると、肥満や生活習慣病の原因になります。
脂質が不足すると、私たちの身体は不足分を補うために、筋肉を分解してたんぱく質をエネルギー源として利用します。
脂質は、油(サラダ油、オリーブオイル、ごま油など)、バター、肉類、魚類などに多く含まれています。
たんぱく質
筋肉や臓器など体の組織をつくる役割があり、炭水化物、脂質と同じく、エネルギー産生栄養素のひとつです。
20種類のアミノ酸が結合した化合物であり、アミノ酸の数や種類、結合の順番によって、約10万種類のたんぱく質になります。
たんぱく質は、体内で消化されることによりアミノ酸に分解されます。
筋肉や臓器、皮膚などといった私たちの身体を構成する材料になったり、身体を調整するホルモン、酵素などの材料や、神経伝達物質のもとにもなっています。
たんぱく質が不足すると、筋肉量や免疫力の低下、疲れやすい、集中力が落ちるなどの状態になります。
肉類、魚類、卵、大豆などに多く含まれています。
ビタミン
体の調子を整える働きがあります。
身体の機能を正常に保つために必要な栄養素です。
ビタミンは、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分類されます。
水溶性ビタミンは、血液などの体液に溶け込んでいるビタミンのことです。
ビタミンB群、ビタミンCなどがこれに当たり、体内のさまざまな代謝に関わっています。
脂溶性ビタミンは、水に溶けない性質を持っており、脂肪や肝臓に蓄えられています。
ビタミンA、D、E、Kがこれに当たり、身体の機能を正常に保つ働きがあります。
摂りすぎると過剰症を起こすので要注意です。
ビタミンは、おもに野菜、果物、きのこ類などに多く含まれています。
なかでも水溶性ビタミンであるビタミンB群は、玄米、レバー・肉類、魚類、野菜に多く含まれており、ビタミンCは、果物、野菜、芋類に多く含まれています。
また脂溶性ビタミンを多く含む食品としては、緑黄色野菜、うなぎ、ナッツ類、ごま、大豆製品が挙げられます。
ミネラル
体の調子を整えたり、体の組織をつくる働きがあります。
ミネラルは無機質とも呼ばれており、骨や血液などといった身体をつくる材料になっています。
また水分調整の役割や、神経・筋肉を調整するといった、身体のあらゆる機能を調整する役割も担っているため、私たちが生きていくうえで重要な栄養素だといえます。
ミネラルが不足すると、さまざまな不調が現れますが、摂りすぎると過剰症や中毒を起こしたりします。
ミネラルは、海藻、牛乳、乳製品、魚介類などに多く含まれています。
まとめ
5大栄養素は、私たちが生きていくうえで、大変重要な栄養素です。
それぞれの栄養素が、それぞれ重要な働きを持っています。
またそれぞれの栄養素が多く含まれる食品もまちまちです。
健康な身体を保つためには、たくさんの種類の食品を食べることが大切です。