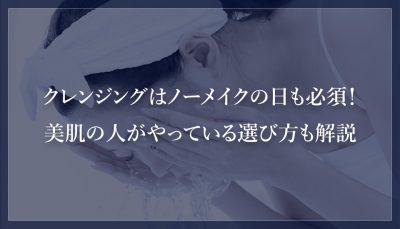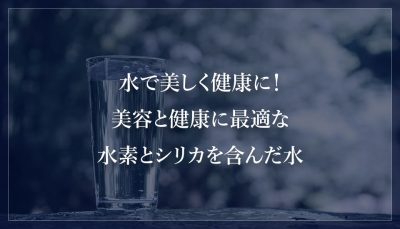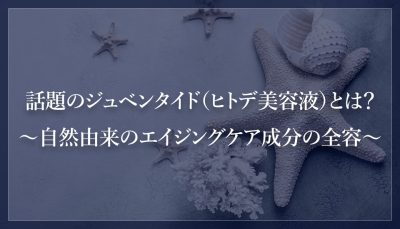完全栄養食とは?五大栄養素について徹底解説
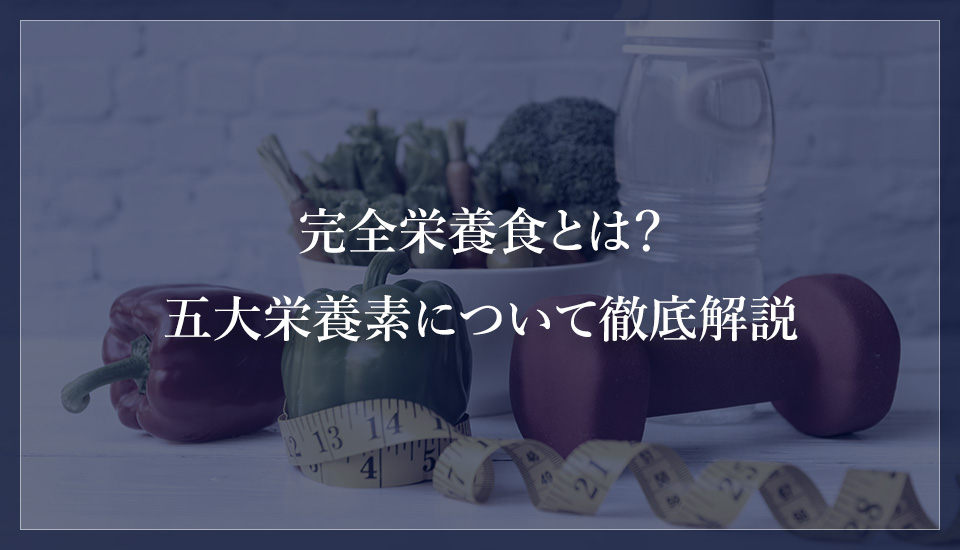
近年よく耳にする「完全栄養食」。
気になっている方も多いのではないでしょうか?
栄養学的な研究や食品加工技術の発展により、サプリメント感覚で摂取できる完全食が登場しています。
これにより、「完全栄養食」は、忙しい現代人が手軽に栄養バランスを整える方法として注目を集めています。
その一方で、実はこの完全栄養食について、誤った認識をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そこでここでは、完全栄養食について5つの観点からご紹介いたします。
ぜひこの機会に、完全栄養食についての正しい知識を知っていただき、日々の食事に上手に取り入れていただければ幸いです。
目次
完全栄養食とは?
完全栄養食とは、人間の健康維持に必要な栄養素をバランスよく含んでいる食品や食事のことを指します。
つまり、それだけを食べていても健康に生活できると考えられる理想的な食べ物のことです。
しかしながら「完全」という言葉は誤解を生みやすい言葉でもあります。
実際のところ、すべての人に共通して「完全」である食品は存在しません。
年齢、性別、活動量、体質、健康状態など、人によって必要な栄養バランスは異なります。
つまり、完全栄養食とは、自分にとっての完全性を目指すことが重要だと言えます。
完全栄養食に含まれる五大栄養素とは?
完全栄養食の定義として、五大栄養素をバランスよく含んでいることが基本条件になります。
それでは、完全栄養食の基本条件となる五大栄養素について詳しく見ていきましょう。
炭水化物
体を動かすための主要なエネルギー源です。
炭水化物が不足すると、疲れやすく、集中力も低下します。
完全栄養食では血糖値が急上昇しにくい低GIの炭水化物が利用されることもあります。
タンパク質
筋肉や臓器、皮膚、髪の毛など体のあらゆる構成要素となる重要な栄養素です。
「完全」と呼ばれるためには、必須アミノ酸をバランス良く含むことが条件に近づくことが重要です。
脂質
細胞膜やホルモンの材料となるほか、脂溶性ビタミンの吸収を助けます。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のバランスが大切で、オメガ3系脂肪酸を含む食品は健康維持に有利とされています。
ビタミン
エネルギー代謝や体調の調整に欠かせません。
ビタミンの種類は全部で13種類あります。
そしてそれぞれが異なる効果を持っています。
例えばビタミンCは免疫機能を支え、ビタミンDは骨の健康に関与します。
完全食においては、通常の食事では摂取しにくい、不足しがちなビタミンを強化している場合が多いです。
ミネラル
カルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウムなどが代表的です。
骨や血液の形成、神経伝達、酵素の働きを助ける役割を担っています。
特にミネラルは、加工食品が多い現代の食生活では不足しやすいため、完全栄養食に含まれていることが大きなポイントとなります。
これらの五大栄養素に加え、食物繊維やフィトケミカル(ポリフェノールなど)が含まれているかどうかも「完全性」を測る基準になりつつあります。
完全栄養食の種類
完全栄養食は、大きく3つのタイプに分類されます。
ライフスタイルや目的に応じて多様な形態の完全栄養食が選ぶことができます。
それでは、それぞれのタイプについて見ていきましょう。
粉末・ドリンクタイプ
飲むタイプの完全栄養食です。
そのまま飲めるタイプや、水や牛乳に溶かすだけで手軽に摂取できるタイプがあります。
粉末・ドリンクタイプの利点は、忙しい朝や外出先でも利用しやすい点です。
食事タイプ
完全栄養を意識して設計された冷凍弁当やレトルト食品、パン、パスタなどがこれに当たります。
普段の食事に置き換えやすく、満腹感も得られるのがメリットです。
最近では「完全栄養パン」や「完全栄養カレー」といった商品も人気を集めています。
固形・お菓子タイプ
バータイプやクッキー、スナック、グミなどさまざまな種類があります。
このタイプのメリットは、間食感覚で手軽に栄養を補える点です。
小腹が空いた時のおやつとしてはもちろん、登山や災害時の備蓄食としても活用可能です。
完全食に近い食材や料理
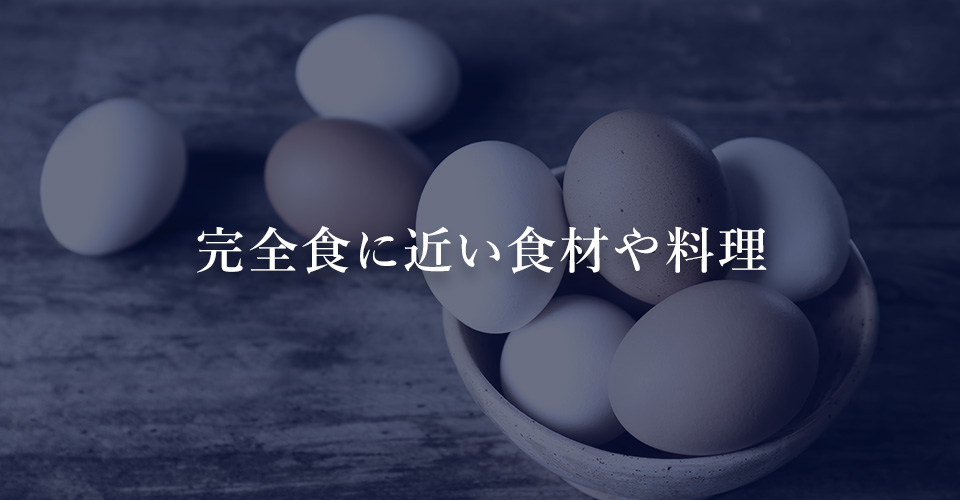
ここまでご紹介したのは、完全栄養食を意識してつくられた食品でしたが、私たちが日頃何気なく口にしている食品や料理の中にも「これだけで生きられる」と言われるほど栄養価が高いものがあります。
卵
卵白には、タンパク質が豊富にふくまれています。
また全ての必須アミノ酸を含んでいます。
一方、卵黄には、脳や細胞の構造に必要な栄養素である、脂質やコレステロールが含まれています。
このほか、白身と黄身の両方に、ビタミンB群やビタミンD、鉄、亜鉛などといいた多くの栄養素が含まれています。
ビタミンCと食物繊維を除き、ほぼすべての栄養素を含むとされ「完全食に最も近い食品」と呼ばれているのが、卵です。
牛乳
カルシウムやタンパク質、ビタミンを含み、栄養バランスが優れています。
また母乳は、赤ちゃんの成長に必要な栄養素がすべて揃っており、自然界における究極の完全食とされています。
玄米
私たちは普段、精米されていない米を食べていますが、玄米は精米される前の米です。
玄米には多くの栄養が含まれており、なかでも玄米に含まれる炭水化物は、消化吸収が比較的ゆるやかなので、エネルギー源として優れています。
また、脂質、食物繊維が豊富なので、腸内環境を整えてくれる役割があります。
このほか玄米にはアミノ酸とビタミンB1、ビタミンB3、マグネシウム、リンなどが豊富に含まれており、栄養バランスが高い食材として知られています。
和食の基本スタイル
和食の基本スタイルとして、一汁三菜(汁物と3種類のおかず)があります。
このスタイルは、多様な栄養素をバランス良く摂取できるため、完全栄養食的な考え方に通じています。
また、玄米+味噌汁のように、雑穀や豆類の組み合わせは、相互に不足栄養素を補うことで「完全食」に近づきます。
完全栄養食と思われているが実は完全栄養食ではない食材
多くの方が「完全食」と思っているが、実際には特定の栄養素が不足している食品も多くあります。
ここからは、実は完全栄養食ではない食材についてご紹介いたします。
| 白米 | エネルギー源としては優秀ですが、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足しています。 |
|---|---|
| じゃがいも | 飢饉を支えた栄養源として知られますが、タンパク質や脂質が不足しています。 |
| バナナ | ビタミンやミネラルが豊富で「完全食」と表現されることがありますが、タンパク質が少なく持続的な栄養補給には不十分です。 |
| スーパーフード(チアシード、アサイーなど) | 特定の栄養素に優れていますが、不足している栄養素もあり「完全」という表現は適切ではありません。 |
| サラダチキン | 低カロリー、低コレステロールでダイエットの味方ですが、脂質や炭水化物、ビタミン、ミネラルが不足しています。 |
| 納豆 | 体に良いとされている納豆ですが、食物繊維、炭水化物、アミノ酸、ビタミンKは摂取できますが、ビタミンB12、鉄、脂質、糖質が不足しています。 |
まとめ
完全栄養食とは、五大栄養素をバランスよく含み、日常生活に必要な栄養を補うことができる食品のことです。
店頭には、粉末やドリンクからお菓子タイプなど多様な食品が並んでいます。
また「卵」や「母乳」のように自然界の完全食に近い食品も存在しています。
その一方で「白米」や「バナナ」のように誤解されがちな食品もあります。
重要なのは、完全栄養食を「万能なもの」と捉えるのではなく、自分の生活スタイルや体質、目的に合わせて活用することです。
適切に取り入れれば、忙しいあなたの健康を支える強力な味方となるでしょう。